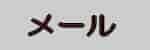福岡市城南区で中国青銅器を買取りました!

★写真はtremolo3247@gmail.com若しくはLINEからお願いします。
◇秋風とともに骨董品を追う…
秋の風というものは、時に財布の中身まで冷やしてくる。
博多の街も例外ではない。木々が色づくころ、私の懐も見事に色づく——青ざめた色に。世間の風は骨董商の肩にも冷たく、通りを歩けば「またガラクタを拾いに来たか」とでも言いたげな視線が、肌にチクチク刺さる。いや、私は拾っているのではない、掘っているのだ。人の家の押入れに埋もれた、時間の化石を。
そんな私に、久しぶりに温かい風が吹いた。一本の電話である。
「もしもし、骨董品の買取をお願いしたいんですけどねえ」
その声は、まるで冬の前に飛び立つ渡り鳥のように優しく響いた。
場所は——福岡市城南区。小高い住宅地。なんともありがたい響きである。
丘の上には金が眠っている、とは古今東西の共通認識だ。もっとも、最近の丘の上はローン返済中のマイホームで埋まっており、金があるのは銀行だけなのだが。
ともあれ私は、電話口の依頼人に言われるがまま、翌朝にはミニバンを走らせていた。冷たい風に顔を刺されながら、私は心の中で唱えた。
「今日こそは当たり日だ。どうか、また七〇年代の工芸皿じゃありませんように」と。
城南区の坂道を登ると、空気の質が変わる。下界より少し上品で、少し古びた香水のような匂いがする。
依頼先の家は、そんな坂の頂きに静かに腰を下ろしていた。
門構えは立派だが、壁の色はやや褪せ、玄関脇の木製表札も字だけが辛うじて読める。古いが、古びすぎていない——この中間の加減が、骨董屋にとっては最高の香りである。
出迎えてくれたのは七十代ほどのご婦人。
「うちはね、戦前は中国の上海で雑貨商をしておりましてね」
と、開口一番に歴史の幕を上げられた。
「へえ、上海でございますか」
「ええ。戦争で全部なくなりましたけど」
と、まるで天気の話でもするように淡々と言われる。
私は頷きながら、心の中で思った。「全部なくなった、という言葉の中に、どれほどの品物と涙が含まれているのか」と。だがそんな感傷に浸る間もなく、ご婦人は続けた。
「戦後はね、中国に残った知り合いを通して、しばらく美術商をやっておりまして。でも先代が亡くなってね、もう畳んだんですの」
“畳んだ”という言葉がやけに静かに響いた。
店を畳む、夢を畳む、そして人の一生もいつか畳まれる。
私はうなずきながら、靴を脱ぎ、畳の上に上がった。
この家にもまた、時間が丁寧に折りたたまれているようだ。
部屋の中は、上海の記憶が漂っていた。
壁に掛けられた中国山水画。棚の上の石獅子の置物。香木のような匂いが微かに鼻をくすぐる。
私はひとつひとつ、そっと触れていく。
まず目に飛び込んできたのは、中国の版画と山水画。
「こちらはどれくらいの時代のものでしょうか」とご婦人。
私は眼鏡をずらし、ルーペを取り出す。
「ふむ……こちらは、七〇年代の工芸品ですね」
と告げた瞬間、ご婦人の肩が少し落ちた。
その様子に私は慌てて続けた。
「ですが、味はありますよ。七〇年代といえば、毛沢東の肖像が街角で笑っていた時代です。その影で、絵筆を握る人々がこうして山水を描いていた。これはこれで貴重な中国文化の断片なんです」
――とは言いつつ、査定額はやや控えめ。
私の口から出る「味がありますね」は、八割方フォローの言葉である。
続いて現れたのは、墨と硯。
呉竹の墨、上海堂の墨、そして端渓の硯。
墨を見れば、人の性格がわかる。使い込まれたものほど穏やかで、未使用のままのものほど野心家だ。
この家の墨はどれも角が丸く、まるで人間の心がすり減ったあとに残るような優しさを持っていた。
硯は、時間の川を泳いできた石。そこにたまった墨の滓が、何十年もの思い出を吸って黒光りしている。私はその重みを手に感じながら、しばし無言になった。

そして、最後に現れた。
一見、ただの花瓶。
だがその姿を見た瞬間、私の鼻の奥がツンとした。
中国の青銅器——。
いや、ただの青銅ではない。
表面に浮かぶ文様は、千年の時間を飲み込んだかのような静けさを持っていた。
中国の青銅器というものは、国家がまだ神に近かった頃の工芸である。
装飾ひとつひとつに「祈り」がこびりついている。
私は、花瓶を手に取り、光にかざした。
薄い埃が金色に舞った。
「これは……まじめな美術品ですね」
思わず口から出た。骨董屋が“まじめ”という言葉を使う時、それは値段以上に敬意を払っている証拠だ。
ご婦人の目が少し潤んだように見えた。
「父がね、上海の友人から譲り受けたものなんです」
「そうでしたか……」
私はしばし花瓶を見つめながら、心の中で誰にともなく頭を下げた。
査定額を告げると、ご婦人は静かにうなずいた。
「そうですか。じゃあ、それでお願いします」
取引成立。
いつもなら、ここで胸の中に小さな勝利の鐘が鳴るのだが、この日は妙に静かだった。
中国青銅花瓶を箱に収めるとき、私はなぜか背中に秋風を感じた。
まるで、花瓶の中に眠る誰かが「これでやっと帰れる」とでも囁いたように。
他の中国掛軸や墨もいくつか買取が決まり、私は道具をまとめた。
ふと見上げると、窓の外に夕陽が傾いている。
橙色の光が畳に落ち、墨の影を長く引きずっていた。
私は、ご婦人に深く頭を下げた。
「ありがとうございました」
「こちらこそ。父もきっと喜んでると思いますよ」
その言葉に、私は苦笑いで応じた。
——喜んでいるかどうかは、神のみぞ知る。だが少なくとも、青銅の神々は笑っていたように思う。
坂を下りる頃、空はすっかり茜色になっていた。
袋の中で花瓶が小さく揺れ、その音が風鈴のように鳴った。
私はミニバンのエンジンをかけ、坂の上の家を振り返った。
あの家の中には、もう一度眠りについた記憶がある。
それをそっと起こしたのが、私の今日の仕事だった。
風が吹く。
私はハンドルを握りながら呟いた。
「人はみな、何かを手放してようやく、本当の価値に気づくのかもしれないな」
そう言って笑った自分の声が、秋風にかき消された。
その瞬間、次の電話の着信音が鳴った。
——風は止まらない。
この青銅器については下記で詳しくお話しておりますので最後までお付き合いください。宜しくお願い致します。
買取品の詳細


◇この「銅器の花瓶」は銘はありませんが時代もあり状態もとてもよく、古い中国銅器によくみられる耳の欠損や口元の欠けなどは見受けられません
買取査定額

◇中国の青銅器の買取査定額もしくは評価額ですがまず第一に刻印と時代、次に状態、ほかには時代の合致した共箱あればより高価買取できます。

ご自宅に中国の花瓶や銅器が御座いましたら一度拝見させてください。もちろん状態や時代、作者、作品でもお値段は変わりますのでご了承ください。
■過去の作品買取例

李王家美術工場謹製花瓶 400,000円
四脚方鼎 300,000円
唐銅 円環耳 花器 80,000円
銀製網火舎 鬼面三足香炉 50,000円 他多数
中国青銅器とは?


中国青銅器の起源と発展
中国の青銅器文化は、世界の古代文明の中でも特に独自の発展を遂げたものとして知られている。その起源は約4000年前、黄河流域の初期文明にさかのぼる。青銅(銅と錫の合金)は製作が難しく、高度な冶金技術と社会的分業体制を必要とすることから、青銅器の出現は文明の成熟を示す象徴ともいえる。中国では、青銅器は単なる実用品ではなく、宗教儀礼や政治権力の象徴として用いられた点に最大の特徴がある。
最古の青銅器は、河南省などで出土する「二里頭文化」(紀元前1900〜紀元前1500年頃)に見られる。この文化は後の夏王朝に比定されることが多く、青銅製の酒器や武器が発見されている。二里頭期の青銅器はまだ装飾が控えめで、実用性を重視した形態が多いが、すでに「爵」「鼎」など、後の時代に儀礼器として定着する器形が登場している。
殷(商)代の青銅器 ― 儀礼と権力の象徴化
本格的な青銅器文化が開花するのは、殷(商)王朝(紀元前16世紀〜紀元前11世紀)である。殷代の青銅器は大量に鋳造され、その精巧さと装飾の複雑さは世界的にも群を抜いている。代表的な遺跡である安陽(殷墟)からは、祭祀に用いられた数多くの青銅器が発見されている。
殷代の青銅器は主に祭祀用の礼器であり、祖先神への供物を捧げるために用いられた。代表的な器形には「鼎(てい)」「方鼎」「爵」「觚(こ)」「鬲(れき)」などがある。これらはそれぞれ肉や酒を供えるための器で、王族や貴族の地位を示すものであった。青銅器に刻まれた銘文(めいぶん)や、表面に施された「饕餮文(とうてつもん)」と呼ばれる怪異な文様は、神秘的で威圧感に満ち、宗教的意味合いを強く持っている。
殷代後期の青銅器の中でも特に有名なのが、「司母戊鼎(しぼぼてい)」である。高さ約1メートル、重さ約875キログラムという巨大な鼎で、世界最大級の青銅器として知られる。この鼎は王族の女性「司母戊」に捧げられたもので、当時の青銅鋳造技術の極致を示す。
周代の青銅器 ― 礼の制度化と文字の発展
殷を滅ぼした周王朝(紀元前11世紀〜紀元前256年)になると、青銅器は単なる宗教的道具から、「礼(れい)」の体系を示す社会制度的象徴へと発展した。周は「礼による統治」を掲げ、身分や階層に応じて使用できる青銅器の種類や数を厳格に定めた。たとえば天子は九鼎を持つことが許されたが、諸侯や卿大夫はそれより少ない数しか持てなかった。青銅器はこのようにして政治的秩序の可視化の役割を果たしたのである。
周代中期以降には、青銅器の形や装飾に変化が見られる。殷代のような怪獣文に代わり、幾何学文様や動植物文様が増加し、全体的に洗練された印象を与える。また、銘文も長くなり、政治的・歴史的事件を記録したものも出現する。たとえば「毛公鼎(もうこうてい)」はその代表で、内側に約500字の銘文が刻まれ、周王の詔勅を記した貴重な史料となっている。
春秋・戦国時代 ― 芸術性と個性の開花
春秋戦国時代(紀元前770〜221年)に入ると、中央の権威が衰え、各国が独自の文化を発展させるようになる。青銅器も多様化し、実用的・装飾的要素が強化された。鋳造技術がさらに進歩し、金・銀・玉などの象嵌(ぞうがん)技術が盛んになる。また、青銅製の武器や鏡も広く用いられ、青銅文化が社会全体に浸透した。
この時代の代表作には、「曾侯乙編鐘(そうこういつへんしょう)」がある。湖北省の曾侯乙墓から出土したもので、65個の青銅製の鐘が調律されており、2,400年以上前の中国が高度な音楽理論を持っていたことを示す文化財である。このように青銅器は単なる宗教具から、音楽・芸術・権威の象徴としての幅広い役割を果たすようになった。
秦漢以降 ― 青銅器の衰退と新たな展開
紀元前221年に秦が中国を統一すると、青銅器の社会的地位は急速に低下した。鉄の使用が普及し、実用品としての青銅器は次第に姿を消していく。ただし、青銅鏡などは依然として日用品・装飾品として製造が続けられた。漢代には「博山炉(はくさんろ)」など、香炉や儀礼具としての青銅器が流行し、写実的で優美な造形が特徴となる。以後、青銅器は実用よりも美術工芸品としての価値を高めていった。
青銅器の美術的価値と現代での人気
中国青銅器は、その造形美・技術力・歴史的意義から、古代美術の最高峰の一つとして高く評価されている。特に殷・周時代の作品は、宗教的荘厳さと抽象的なデザイン性を兼ね備えており、近代以降、国内外のコレクターや美術館により熱心に収集されてきた。
現代では、以下のような青銅器が特に人気を集めている:
-
司母戊鼎:殷代最大の青銅器で、中国古代文明の象徴。
-
毛公鼎:長文の銘文を持つ周代の代表作。歴史資料としても重要。
-
四羊方尊(しようほうそん):殷代の立方体型の酒器。四隅に羊の頭部が装飾され、造形美が際立つ。
-
曾侯乙編鐘:音楽文化の粋を示す青銅楽器。
-
銅鏡・博山炉:漢代以降の工芸的発展を示す作品。
こうした青銅器は、中国の国家的遺産として厳重に管理されており、北京の故宮博物院や上海博物館などで鑑賞することができる。また、模造品や復刻品も人気で、伝統文化を象徴するインテリアとしても親しまれている。
■参考サイト
■その他の買取品目
★骨董品買取の福岡玄燈舎では古美術品の他、アンティークや掛軸、茶道具、書道具、絵画、仏像、勲章、中国陶磁、甲冑など多彩な骨董品を査定買取しております。お見積りだけでも構いませんのでお気軽にご相談ください。